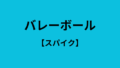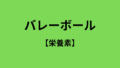お疲れ様です
「ブロックのコツが知りたい」
「ブロックをしても上手くいかない」
このような悩みを解決できる記事を用意しました。
はじめまして、self-studyと申します。
バレーボール歴は25年で、資格は1次、2次、日体協資格を持っています。
小学生の指導を3年間、中学生の外部指導者を1年間していました。
全国大会の実績を数多くもつ監督さんに弟子入りし学んだノウハウと自身の経験を元に「地区大会で1ケタの点数しか取れないチームを県のトップレベルのチームに育てる方法」を日々配信しています。
今回の解決方法はブロックの基本と仕組みを理解するというものになります。
実際に僕が指導にあたっていたチームもこの仕組みを実践して、しっかりと連携のとれるブロックができるようになりました。
記事の前半ではブロックの必要性と基本について、記事の後半ではブロックの目的と実戦で使う技術について書かれています。
ぜひこちらの記事をお読みになり日々の練習に活かしていただければ幸いです。
ブロックとは?

ブロックとは相手の攻撃に対しネットのそばでジャンプして、さえぎることです。
ブロックは普段の練習でおろそかになりがちな技術ですが、中学生、高校生では確実につかいますので小学生の早い段階で身につけてもらいたいものです。
またゲームの流れを大きく変えるスキルでもあります。
僕が教えていた小学生のチームでは、ブロック1本でゲームの流れがかわり逆転したケースがよくありました。
ブロックの必要性
ブロックは必ず必要になってくる技術です。
バレーボールが高度になってくると読みだけのレシーブでは相手にとって好条件になり厳しいゲームになってきます。
そこでブロックとレシーブで連携をとりディグフォーメーションという形をとります。
このフォーメーションを組めばレシーバーの範囲も明確になりますし、相手も単純な攻撃ができなくなります。
このようにブロックはチームにとって大事になってきます。
ブロックの基本
構え方
足を肩幅に広げ、ヒザを軽く曲げます。
手のひらを相手に向けるようにだします。この時に肘が肩の高さよりも低くならないように気をつけましょう。
構えた時に肩甲骨を意識してあげておくこともポイントになってきます。
立ち位置
構えの立ち位置は両腕を伸ばしてネットに触れるぐらいの距離です。
近いと視野もせまくなりますしブロックをした時に近づきすぎているため、あおるような形になってしまい、遠くなりすぎるとステップを踏みずらくなります。
繰り返しになりますが、構えの立ち位置は両腕を伸ばしてネットに触れるぐらいの距離からステップを踏むことが大事になってきます。
ブロックの空中姿勢
空中姿勢では弓形を意識すること、肩甲骨をあげて最短距離でだしていくことが大事になってきます。
それぞれ解説します。
空中では弓形(くの字)の形をイメージ
ブロックでは空中姿勢として弓形(くの字)の形をとり、体幹をしめます。
逆にしてはいけない形は顎があがり体をそらせた(あおる)形です。
この形は立ち位置の時点でネットに近づきすぎている場合も多いためタッチネットの反則のリスクもありますし、ボールの勢いにも負けてしまいます。
もしこのような悪い形のくせがついた場合は、空中で「つま先を上にあげる意識」をもつこと、「ふところに空気を抱くようなイメージ」をもつことで改善されます。
肩甲骨をあげて最短距離でだしていく
手を出すときは肩甲骨をあげて最短距離でだしていくことも意識します。
これは手をだすだけの場合と肩甲骨を上げて出していく場合では到達点がおよそ5センチ変わってくるためです。
また最短距離というのは正確にブロックができるように後ろや横からだすのではなく、なるべく構えの姿勢からそのままだしていくということになります。
戻すときも同様に最短距離で戻します。
ブロックをする時の手の形
床に置いたボールを手前側からつかみ、そのまま頭上にもってきて離します。
この時の手の形が基本の目安になります。
またこの目安はブロックの目的別に形が変わってきたりします。
ブロックの目的
ブロックをする場合は選手の能力やチームの戦術として目的をきめて行います。
キルブロック
相手のスパイクを止める目的としてブロックをおこないます。
キルブロックの手の形は尺屈と呼ばれて、親指が上にむいた形です。
この形は手を後ろにもっていかれにくく相手スパイカーのパワーにも負けないようにすることができますが、親指が前にきて突き指をする可能性がありますのでしっかりボールの形にあわせるイメージをもって突き出していきましょう。
ソフトブロック
相手がスパイクをするボールに少しでも触って勢いを弱めようとする目的でブロックをおこないます。
この時の手の形は背屈と呼ばれて、手首を後ろへ返した形です。
エリアブロック
攻撃をする選手はブロックをされないようにブロックをする選手の横を打ったりします。
そのコースにレシーブをする選手が入るなど、ブロックとレシーブをする選手の連携を視野にいれてブロックをおこないます。
プレッシャーブロック
ブロックをする行為そのもので相手にプレッシャーをかけ、ミスをさそう目的でブロックをおこないます。
実戦で使うブロックの技術
ステップ
ブロックには移動するステップのとりかたが4つあります。
クイックワン
横に1歩ふみこむステップになります。
サイドステップ
横にサイドステップで移動していきます。
ふみこむ順番として、右に行く場合には「右、左、右」
左に行く場合には「左、右、左」となります。
足は交差させないように気をつけます。
ワンステップクロスオーバー
横に1歩ふみこみ2歩目は足を交差させて3歩目に交差させた足をもどします。
サイドステップ+クロスオーバー
②番と③番を合わせたステップです
順番としては、右に行く場合「右、左、右、左交差、右元に戻す」
左に行く場合は反対となり「左、右、左、右交差、左元に戻す」
となります。
ターンイン
ステップを踏んでブロックに跳んだらターンインをすることも意識します。
ターンインとはブロックの完成時に外側の手を内側にむけていく技術になります。
この技術ができていないとワンタッチでブロックアウトをおこす場合が多いです。
そのためターンインをしてブロックしたボールが相手コートの中におちるようにします。
ブロックの隊形
スプレッド
等間隔に広がって配置した隊形です。
両サイドからの攻撃には対応できますが中央からの速い攻撃の対応は難しくなります。
バンチ
中央付近に配置した隊形です。
基本的には全ての攻撃にたいして常に2~3枚のブロックで対応していきます。
中央付近に集まっていることで真ん中からの攻撃には効果的ですが、両サイドからの速い攻撃の対応は難しくなります。
デディケート
相手チームの攻撃パターンに応じて配置した隊形です。
例えば、レフトのエースが中心でライトの攻撃もある可能性がある場合は始めからレフトに2枚、ライトに1枚つく形になります。
このようにブロックをする選手の間隔を均等にせず、相手攻撃の特徴にあわせてそこにブロックの人数を増やす方法です。
スタック
前に2人、後ろに1人配置した隊形です。
コンビネーションを使ってくるチームに対応したもので、前の選手はクイックを仕掛けてくる選手をマークして後ろの選手は相手のクイック攻撃後の時間差攻撃に対応します。
相手の動きに合わせてブロッカーも入れ替わったりするので切り返しの攻撃が難しくなります。
ブロックの反応
リードブロック
相手チームのトスが上がったボールに対して動いていきブロックをします。
コミットブロック
コンビネーションを使って速い攻撃をしてくるチームに対してリードブロックを行うと間に合わなくなります。
そこで相手チームのトスの行方を判断する前に跳ぶコミットブロックが用いられます。
このブロックの特徴はクイックで入ってくる人に対して跳ぶことです。
トスに振られるデメリットもありますがスパイクを打つ選手にたいして確実に1人以上でブロックできるため、クイック攻撃での対応に適しています。
複数でブロックをするときの注意点
複数でブロックをするときの注意点は、間をあけないようにすることです。
隣り合うブロックをする選手の間が空くとスパイカーもそこを狙ってきますし、味方のレシーバーも空いた所に入っていく必要がでてくるためフォーメーションが成立しなくなります。
間を空けないようにするには2つのポイントを意識します。
間を空けないようにする2つのポイント
・跳ぶ前は腰から当てにいくようなイメージで移動をして間をつめる
・空中では手を交差させるイメージと肩どうしを付ける意識をもつ
これら2つを意識してブロックを行います。
また間をつめるには早めに外側の選手が位置決めを行ってそこに中の選手が合わせていくということも必要になってきます。
まとめ
・ブロックの基本的な構え方や立ち位置と空中姿勢、手の形作りをマスターする。
・ブロックをする目的にはキルブロックやソフトブロック、エリアブロック、プレッシャーブロックがある
・ブロックのステップはクイックワン・サイドステップ・ワンステップクロスオーバー・サイドステップ+クロスオーバーをつかう
・ターンインを意識する
・隊形にはスプレッドやバンチ、デディケート、スタックがある
・リードブロックとコミットブロックを使いわける
・複数でブロックを行う場合には2つのポイントを意識して間をつめる
これらを意識していくことでブロックのレベルをさらに上げていくことができますのでぜひ実践してみてください。
ちなみに今回の記事でははこちらの本とDVDの第6巻でやり方がさらに細かく載っています。
DVDはこちらの本を全て映像化して解説しているものとなっていますので全6巻セットでの購入がおすすめです。
是非参考にしてみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。

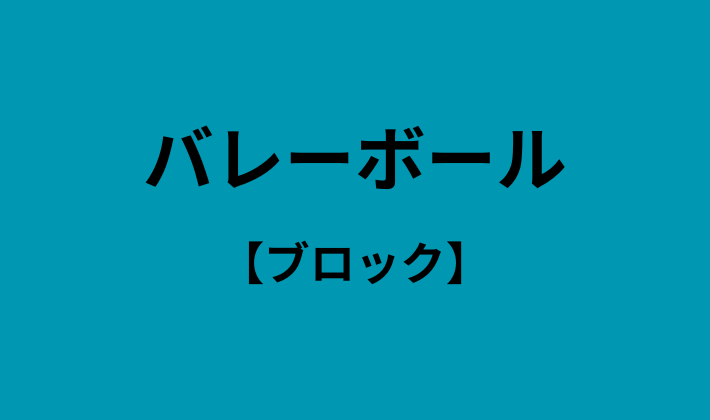
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2fa51a56.71bb4c83.2fa51a57.ae9ceaa8/?me_id=1263594&item_id=10001870&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjapanlaim%2Fcabinet%2Fsports%2Fsports_dvd.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)